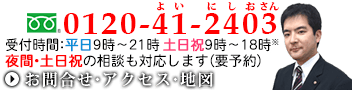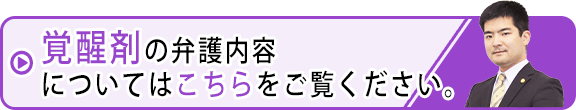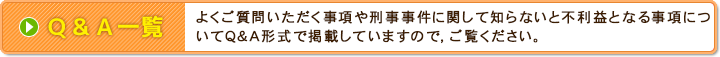「薬物犯罪」に関するお役立ち情報
覚醒剤で逮捕されたら
1 覚醒剤事件について
薬物事件における「薬物」にはいくつか種類があります。
その中でも、覚醒剤事件(覚醒剤事件)については特に重い刑罰が規定されています。
薬物常用者には、幻聴、慢性の幻覚、妄想状態などの症状が現れ、これにより、自己や他者を傷つけてしまうことや、殺人や放火等の凶悪犯罪を引き起こす引き金となることがあるといわれています。
そのため、覚醒剤や大麻等の薬物事件は、他の刑事事件と比べて重大な犯罪と評価され厳しく規制されているのです。
今回は「覚醒剤(覚醒剤)」について、逮捕のきっかけから判決までの流れについて解説します。
2 覚醒剤取締法違反の法定刑
まず、覚醒剤取締法違反となる主な行為とその罰則は以下のようになっています。
【輸出入、製造】
非営利目的の場合:1年以上の有期懲役
営利目的の場合:無期又は3年以上の懲役刑。情状により1000万以下の罰金が併科される可能性がある
【譲渡、譲受、所持、使用】
非営利目的の場合:10年以下の懲役
営利目的の場合:1年以上の有期懲役刑。情状により500万円以下の罰金を併科される可能性がある。
【原料の輸出入、製造】
非営利目的の場合:10年以下の懲役刑
営利目的の場合:1年以上の有期懲役刑。情状により500万円以下の罰金を併科される可能性がある
【原料の譲渡、譲受、所持、使用】
非営利目的の場合:7年以下の懲役刑
営利目的の場合:10年以下の懲役刑。情状により300万円以下の罰金を併科される可能性がある3 覚醒剤使用・所持が発覚し逮捕される理由
覚醒剤の所持・使用などが発覚するきっかけには、様々なものがあります。
多いのは、検挙件数の多い地域などでの、職務質問・所持品検査です。
キョロキョロして落ち着きがなく挙動が不審である場合などに職務質問が行われます。
質問に対して要領を得ない返答であったり、ことさらに質問を拒否して立ち去ろうとしたりする場合は、疑念が深まり、所持品検査が行われます。
そして、覚醒剤、容器、注射器などが発見された場合、簡易鑑定が行われ、覚醒剤反応が出れば現行犯逮捕されます。
尿検査をして覚醒剤の陽性反応が出た場合も同様です。
次に、売人や常習者が逮捕されて、所持していた携帯電話番号をきっかけとして販売ルートに対する内偵捜査が進み、逮捕されたというのもよくあります。売人や中毒患者からの密告も珍しくありません。
さらには、突然意味不明なことを言い始めたため、家族が精神科を受診させた結果、精神病ではなく覚醒剤の影響であることが分かり、家族が更生のために警察へ通報したり、覚醒剤の使用を知った会社の同僚・恋人等身近の者が警察に通報したりするというのもよく聞かれます。
なお、警察官による捜査の他に、厚生労働省の麻薬取締官は、警察官と同様の捜査権限(逮捕・押収など含め)を有しています。
麻薬取締官も、覚醒剤やその他違法薬物犯罪の捜査に当たり、警察と同様の捜査活動を行っています。
俗に「麻薬Gメン」「マトリ」と呼ばれており、これよって覚醒剤取締法違反の容疑者を逮捕する場合も多くあります。
4 覚醒剤で逮捕された後の手続きの流れ
⑴ 警察官による逮捕、検察庁への送致
警察官に覚醒剤に関する罪で逮捕されると、警察署などで取調べを受けます。
その後、逮捕後48時間以内に、所轄の検察庁に送致の手続きがとられます(送検)。
⑵ 検察官の弁解録取、勾留請求
被疑者が検察庁に送致されると、検察官は、当日中に犯罪事実についての被疑者の弁解を聞き、(逃亡や証拠隠滅の可能性があるなど)勾留の必要があると考えられる場合は裁判所に勾留請求を行います。
⑶ 勾留と起訴
勾留請求を受けると、裁判官は、被疑者に対し勾留質問を行い、勾留を決定します。
勾留の期限は10日間ですが、薬物事件の場合はこれだけでは捜査に必要な日数が足りず、さらに10日間の延長をされるのが通常です。
つまり、勾留が決定されると20日間、警察署に身柄が拘束されます。
この間に検察官は、家宅捜索などの捜査や、必要に応じた取り調べを行っていきます。
覚醒剤や麻薬などの薬物犯罪は薬物の成分の本鑑定が必要です。
鑑定結果が出るまでの期間は、その地域で検査を担当する科学捜査研究所の体制や鑑定依頼の混み具合により、早い場合も遅い場合もあります。
そのため、勾留は、最低でも鑑定結果が出るまで続きます。
例えば、本鑑定で、尿から覚醒剤の成分が検出された場合には、検察官が裁判所に対し、被疑者を覚醒剤自己使用の罪で起訴することになります。
⑷ 公判手続き
起訴されると、被疑者は、被告人と呼ばれるようになります。
そして、起訴後約1~1か月半後に、第1回公判期日が開かれます。
覚醒剤事件の場合、否認していない限り、通常、公判は1回で結審します。
次回期日は、1~2週間後くらいまでの間に開かれ、判決が言い渡されることになります。
ケースによりますが、軽微な事案で犯行を認めており、証拠調べも速やかに終わることが見込まれる場合には、検察官が被告人の同意を得た上で、第1回公判期日に即日判決が言い渡される「即決裁判手続」を選択することもあります。
初犯の覚醒剤の自己使用目的所持・自己使用である場合は、懲役1年~2年に執行猶予がつくのが通常です。
もっとも、多量の所持の場合には、執行猶予がつかない実刑の可能性もあるので油断できません。
5 覚醒剤事件の弁護活動
⑴ 身体拘束からの解放
上述したように、被疑者が逮捕されてから起訴されるまでの間、最大で23日間、被疑者は身柄拘束され続けることになります。
痴漢等であれば、弁護士が検察官や裁判官に対して釈放を働きかけたり、裁判官が勾留決定を下した場合でも、準抗告という手続きを裁判所に申し立てたりすることにより、裁判官の行った勾留決定の取消しが認められて釈放されることもあります。
しかし、覚醒剤事件の場合、検察官や裁判官への釈放の働きかけはもとより、この準抗告の手続きが功を奏することはあまりないといえます。
また、覚醒剤事件は不起訴になる場合が少ないことも一つの特徴です。
そうすると、弁護士ができる被疑者の救済手段としては、保釈(保釈金の納付等を条件に身体拘束から解放される制度)の手続きを起訴後いかに迅速に行うかにかかっています。
これをスムーズに行えば、起訴後の比較的早期の段階で被告人を釈放することができます。
⑵ 執行猶予の獲得と再犯防止
覚醒剤事件の具体的な弁護方針は、執行猶予を獲得することです。
執行猶予付きの判決を獲得することで、実刑を回避することができます。
薬物事件では、被害者がおらず示談が観念できないのが通常なため、再犯防止についての措置を講ずることが非常に重要です。
これは、執行猶予付き判決を得るためだけでなく、執行猶予が取り消されないようにするためにも重要です。
執行猶予判決執行猶予判決となり無事社会復帰できたのに、再び覚醒剤に手を染めてしまうと、再び覚醒剤使用で実刑判決になり、また執行猶予も取り消されますので、少なくとも3年から4年は服役することになってしまいます。
覚醒剤に再び手を染めないように、薬物関係の依存症の治療に重点を置いている病院やクリニック(心療内科など)での治療や、ダルクといった更生支援施設での更生、他に没頭できることを見つけて覚醒剤に頼らない生活を送るなど、自らを管理し、二度と覚醒剤には手を出さないようにしていく必要があります。
そこで、弁護士は病院の紹介や、本人や家族等に再発防止のための助言も行います。
窃盗で捕まったら弁護士に相談すべき理由と弁護士費用相場 身に覚えのない大麻所持で逮捕されたら